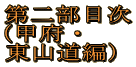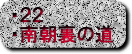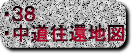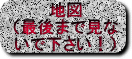興国五年(1344)四月。遠江国千浜。その名の通り、千の砂丘が形成されるほどの長大な砂浜が続く。(現在、静岡県掛川市大東の千浜砂丘、ただし砂丘としては比較的小規模)晴れてはいるが寒い日であり、さらに風が猛烈に強い。そのため体感温度は案外低い。にもかかわらず、薄 手の羽織だけをまとった僧侶らしき人物がひとりきりそこに立っていた。実はこの僧、浜から内陸に約一里ほど入った金剛山貞永寺(現在も金剛山貞永寺)の雲水である。ひたすら細く粒の揃ったきれいな砂を手で握り、拳の小指の下の隙間から少しずつ砂を落とし風に舞わせていた。僧はそんなことを朝から何度となく繰り返しているのである。あきもせずひたすらに同じことを繰り返している姿は普通ではない。時折、僧は手を止めて、海岸線のはるかかなたの西を望んでいた。
手の羽織だけをまとった僧侶らしき人物がひとりきりそこに立っていた。実はこの僧、浜から内陸に約一里ほど入った金剛山貞永寺(現在も金剛山貞永寺)の雲水である。ひたすら細く粒の揃ったきれいな砂を手で握り、拳の小指の下の隙間から少しずつ砂を落とし風に舞わせていた。僧はそんなことを朝から何度となく繰り返しているのである。あきもせずひたすらに同じことを繰り返している姿は普通ではない。時折、僧は手を止めて、海岸線のはるかかなたの西を望んでいた。
* * *
時は前後するが、延元四年(1339)伊勢国篠島から日野大僧正頼意とともに義良親王は吉野に無事帰還した。御味方が次々と倒れる中、義良親王と北畠顕信の帰還は吉野を喜びに沸きかえらせた。帝(後醍醐天皇)にとっても、最愛の阿野三位局廉子の長子義良親王の帰還である。他のいかなる御子の無事よりも嬉しかったに違いない。そこで帝は義良親王を立太子させ皇太子となした。これが運命の機微というものであろうか。
顕信にとっては、そもそも義良が皇太子になることは想定の範囲内ではあり望むべくことであったが、その時が来るのが思いのほか早かっただけである。やはり廉子の子であることが有利に働いたのか。しかし、その後、その顕信の想定なぞはるかに超越した事態があまりにも早く生じることになる。
八月に入って直ぐに帝は病の床に伏してしまった。そして八月十六日 には、
玉骨はたとひ南山(吉野)の苔に埋るとも、 魂魄(こんぱく)は常に北闕(ほくけつ:京都)の天を望まんと思ふ <太平記>
と遺言を残し吉野の行宮(あんぐう)にて崩御してしまったのである。 後醍醐天皇は病の中、死期を悟り死の前日に皇位を義良親王に譲位することも遺言した。実際には同年十月三日に伊勢神宮へ奉幣使(ほうへいし)をつかわされ、皇太子が天子に即位された。天子即位の受禅にはかねてより有職故実に基づき種々の儀礼があり、それは数年に及ぶのが通例なのだが、いかんせん、京から離れた山里の吉野である。結局、天位の受禅といっても形ばかりで三種の神器を拝されたのみで皇太子義良は新帝(後村上天皇)となった。御歳は若干十二歳であった。
この義良親王の新帝即位は顕信の想定をはるかに越えたものであった。とは言え、顕信は篠島にいるころから万が一でも義良親王が帝に即位した場合の懸念をおぼろげに考えていたのだが。それは、井伊谷の三岳城に入城している一品中務卿宗良親王との微妙な関係である。宗良親王の方が年上で、この宮は今後、着実に信州の基盤を固めて行くであろう。この宮であれば南朝の有力者を掴み皇位を奪うことは十分可能であろう。それどころか、顕信の誇大妄想癖によれば、もし仮にである、あくまでも仮だとして、一品中務卿が足利尊氏ら北朝側と結託した場合、南朝の新帝と北朝持明院統の光厳上皇一族をいっさいしりぞけ一挙に持明院統、大覚寺統の統一、つまり南北朝の統一を果たした上、自らが帝位になることもありえるのではなかろうかと。顕信はもし自分が一品中務卿の立場であれば十分に考え得る戦略であると思えた。しかも北條氏残党勢力と呼応できるのである。北朝と勝手に和睦でもされたら大変なこととなる。またいかにもそれは現実的な話であるとも思えた。
がしかし、今の顕信には仮にも御味方である一品宮(一品中務卿宗良親王)を疑い、かつそれに見張りをつけるなどという余裕はなかった。それにまず顕信は、味方である人物に嫌疑をかけること自体が許されざる卑劣な行為に思えた。先帝の大塔宮に対する嫌疑が南朝の衰退を加速させたと常々考えている顕信である。味方に疑いの目を持つこと自体が嫌悪の対象であるにもかかわらず自分がそのようなことをして良いのであろうか。自問自答で悩み多き青年である。花将軍と歌われた兄顕家であれば、あるいは今般の東国遠征で無事目的地に到達した父親房であれば。彼らであればいったいどうするであろう。悲しいかな顕信の決断基準とはこのようなものである。でも結論は変わらなかった。今は一品宮に対して何もすることはない、いやすべきではない。当面様子見であると。
そもそも、顕信は義良親王が帝に即位した頃から、再び軍勢を立て直し鎮守府将軍として東国遠征するための準備で忙しかった。千賀地に命じ、また伊勢国大湊光明寺の恵観に命じ兵糧、軍船の準備に明け暮れていた。そしてその翌年、興国元年(1340)五月。再び顕信は大湊を出港した。一昨年の時とは異なり陸奥宮は乗船していない。基本的なルートは神島の沖を越え、さらに御前崎を越え、伊豆半島、房総半島を越え常陸に上陸するというものだ。常陸の小田城(現在、茨城県つくば市)にいる父北畠親房に会い公式に新帝即位を伝えるとともに、種々の情報を交換する。その後、状況に応じて陸路、あるいは海路で石巻に向かい陸奥に入城する計画であった。そして実際に夏には顕信は陸奥国日和山城(現在の宮城県石巻市)を根拠地として南部、葛西、
伊達などの南朝方豪族とともに奥州経営の任にあたることとなったの
である。
* * *
義良親王が立太子したちょうどその頃、一品宮は遠江国井伊谷の三岳城に入城し遠江引佐郡一帯に基盤を築きつつあった。しかしこれを北朝側が許すわけがない。延元四年(1339)七月二十二日、尊氏卿の命を受けた高師兼軍が鴨江(かもえ)城(現在の浜松市の高野山鴨江寺)を攻撃。この城は三岳城の支城のひとつで城とは言え鴨江寺の土塁を城の土塁とし寺の伽藍を曲輪としあとは付け足しで骨組みだけの物見櫓を付随させただけの代物。籠城もままならず五日にしてあえなく落城。鴨江寺は先の大戦のおりに先帝から寺領安堵の綸旨を受けていたにもかかわらず散々に荒らされてしまったのである。これを皮切り南朝遠江の崩壊が始まる。次に一品宮は井伊氏討伐のために下ってきた高師泰、仁木義長らと開戦。そして先帝崩御、新帝即位の頃までには戦況が著しく悪化、10月30日には千頭峯城、翌興国元年(1340)1月30日にはついに本城である三岳城が落城。さらに顕信が東国に着任した8月頃には詰城である太平(おいだいら)城が落城。結局遠江の拠点を全て失い駿河の安倍城を経由し一品宮は越後国寺泊(新潟県長岡市)まで落ちていく。
一方、遠江のこの戦争に呼応する形で、北條高時の遺子であの中先代の乱の首謀者でもある相模次郎(北條)時行が懲りずに鎌倉奪還を目指して信濃国大徳王寺城(現在、諸説あるが長野県伊那市長谷の常福寺)で挙兵した。しかし信濃国守護で伊奈を本拠とする小笠原貞宗が対戦し、相模次郎時行らは4ヶ月間に及ぶ籠城もむなしく10月23日に大徳王寺城は落城した。
敵の敵は味方である。北畠顕信が頭の中でシミュレーションしていたように、あるいは南朝方の当然の戦略として、これら北條残党勢力を束ね味方とすれば相当な戦力となる。これもまた、顕信が篠島で一品宮の遠江入りを聞いたときに思っていたことではあるが、再度遠江を奪還すれば、伊勢から遠江まで海路、そこから天竜川伝いに諏訪までの南朝街道が開かれる。自然とこの大戦略の遂行者は地理的に一品宮となっていく。
興国四年(1343)、ついに一品宮は大戦略を実行するため越後寺泊を発した。そして飛騨、木曾を経由して信濃国伊奈郡大河原(現在の長野県伊那郡大鹿村)入をした。この宮はこの大河原を本拠地としてこの後、三十年間も南朝方として戦い続けることになる。故にこの一品中務卿宗良親王は信濃宮と称されている。
信濃宮は皇子で武人であるとともに歌人でもある。自身この頃の思いを歌に詠んでおり、後に李花集としてまとめている。山里の城で聞いた鶯で、京都で聞いた鶯の声を思い出したのであろう。
興国五年信濃国大川原と申す山のおくに籠居侍はべりしに、ただ仮初なる山里のかきほわたり見ならはぬ心地し侍るに、やうやうわかぬ春の光待ち出づる鶯の百囀も昔思ひ出でられしかば
かりの宿 かこふばかりの 呉竹を
ありし園とや 鶯のなく
また、伊奈郡で花見をしたときの思い出も記している。
信濃国伊那郡と申すところにて花み侍りしに思ひ出で侍りける
散らぬまに 立ち帰るべき 道ならば
都のつとに 花も折らまし <李花集>
* * *
興国四年(1343)、信濃宮が大河原に入城した頃、東北の顕信は三迫(さんのはざま)合戦で大げさに言えば一敗地に塗れてしまい、次の作戦行動を思案していた。その頃、悪いことは続くもので関東では、同年11月に高師冬ら北朝軍の兵糧攻めに絶えかね関宗祐(せきむねすけ)が守る関城(茨城県筑西市)と下妻政泰が城主の大宝城(茨城県下妻市)が陥落した。この陥落、元来味方であった結城親朝(あの結城宗広の嫡男)の寝返りによるところが大きい。実は顕信の父北畠親房はまさにこの関城に居たのである。親房は関城からかろうじて脱出。海路で尾張国知多のウバメガシに覆われた幡豆崎城にたどり着いた。篠島は直ぐ先である。伊勢神宮の外宮禰宜である度会家行に救出を求め、家行の保護を得て親房はなんとか吉野まで落ち延
びた。
常陸での拠点喪失は顕信にも大打撃であった。常陸は陸奥と西方を結ぶ拠点であり、そこから吉野や京の情報を得ていただけに。顕信から見た場合、吉野に通ずる南朝側の拠点は東山道経由での信濃大河原だけということになった。
ここに至り、鎮守府将軍顕信も信濃宮の動向に注目せざるを得なくなっていった。間接的に幾つかの方法で宮の情報を得ることは可能であるが、自分の目で、耳で、足で動向を知りたかった。むろんそれは不可能である。また宮のみならず足利方全体の動静の情報が欲しかった。
間者を使う時がきた。自分の目や耳に近い間者を。顕信は座右にいつも置いている蓋に螺鈿のある箱を見やった。それは彼しかいない。
伊勢大湊を出港した時から、伊賀の千賀地党の者数人が常に顕信に同行していた。そのもの達に目西を探し出し、ともに北朝方の動向はさることながら、信濃宮の動向をも見張るようにと命じた。見張る位置その他委細、すべて目西に任せるというものだった。
* * *
興国五年(1344)四月。遠江国千浜。はるかかなたの西を望んでいた雲水は金剛山貞永寺に戻っていった。
南朝裏の道
後世の秋葉街道=国道152号線
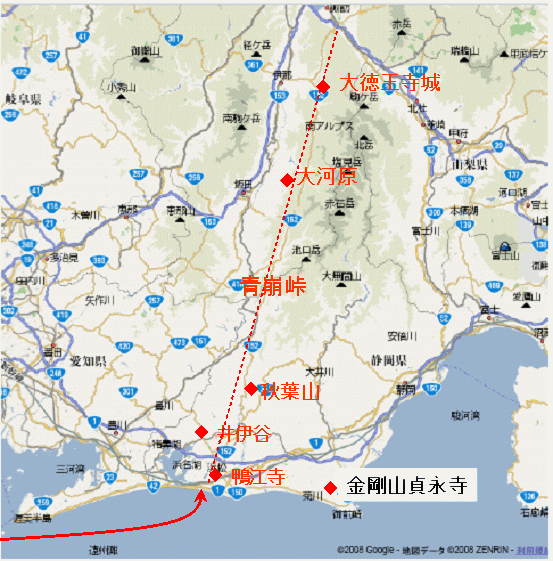
Copyright(c) 2019. Gigagulin (偽我愚林)