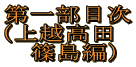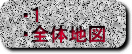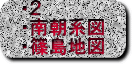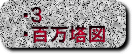この島に漂着して何日経ったのであろう。あれから幸い嵐もなく、また風はいつのまにかすっかり秋風になっている。そして夜更けには涼しげな虫の音が聞こえる。島ののどかな風景とは逆に顕信は焦燥に駆られていた。どうすれば島から脱出できるのであろう。どうすれば迎えが来るのであろうか。親王の令旨を各地に発すれでもすれば良いのか。こんな時、父親房なら、あるいは兄顕家ならきっと無難に対処しているに違いない。それに較べて自分は。
顕信は実兄顕家の活躍をいつも影で見つめていた。つい数ヶ月前にその兄が二十一歳の若さで敗死するまでは。その兄が死ぬことなど到底想像もつかなかった。そしてまた自分が戦の表舞台に出て指揮をとることなど考えてもいなかったことである。
兄は幼少の頃から才気に恵まれていた。目鼻立ちも良く人々からは花将軍と称されていた。出世もずば抜けて早く、史上最年少の十四歳で正四位上参議である。未だに吉野行宮(よしののあんぐう)で多くの人の語り草になっている。
そう、この兄が参議に叙せられた元弘元年(1331)春。西園寺公宗公の北山邸(現在の金閣寺)で帝を迎えての花宴のこと。舞楽が奉納されるおり、顕家は回りから押され晴れの舞台に上がり一つ舞うことになった。即興である。美少年と言われる彼に相応しく舞は「陵王」となった。
この舞、舞人一人、左方唐楽、走り舞。中国、北斉の蘭陵王長恭が、あまりにも美貌なので、戦の際には竜の仮面をかぶって戦った故事にちなむという。勇壮かつ華麗な舞。
時折の風が吹くと桜の花びらが散る。笙の音、陵王の面、夕星(ゆうづつ)が映える晴天の夕暮れ。帝は春の暮れ時の寒さも忘れ、この幽玄の世界で上機嫌だったのであろう。顕家の舞に合わせて自らも笛をとられた。
暮れかかる程に、花の木の間に、夕日花やかに移ろいひて、山の鳥の声もしまぬ程に、陵王の輝き出でたるは、えもいはずおもしろし。その程、上(帝)も御引直衣にて椅子につかせ給ひて、御笛吹かせ給ふ。常より殊に雲井をひびかすさまなり。宰相中将顕家、陵王の入稜を、いみじう尽くしてまかんずるを。
<増鏡>
目西こそ類まれな異能の者。顕信は井の件より、いや実はそれ以前からそれを感じていた。彼の持つ正確な観察眼と筋の通った論理構成。そして父から聞いた話では彼は異母兄弟。また彼は異質の忍者でもある。顕信はこの難局に目西なら解をだせるのではないかと感じた。そして島長をあえてよばず神職二見に目西を呼びに行かせた。島長を呼ばずに目西にこの窮状の相談をするということに神職は理解を示した。二見も神宮禰宜の度会家行の門下生。また天下の伊勢神宮の神職。人を見る目はある。二見の目にも島長より目西のほうがはるかに物事の本質を見抜いていることはかねてから感じていた。あるいは、それは自分自身やこの若い鎮守府将軍以上かもしれないと。確かにこの埒のあかぬ窮地に異質の知恵が生きる可能性はある。
医徳院の講堂で顕信が状況を一通り説明している間、目西は絶えず西を向き決して話者を見ることがなかった。そして話が終わると一言、
「密書を伊賀神戸(いがかんべ)の忍家に渡せばよい」
と言った。すぐさま顕信が二見の言を制止しようとしたのをあえて切り二見が質問をした。
「どのようにして密書を伊賀まで送るのか」
確かに、二見が質問するのも尤もである。篠島から書状の類を送付することは極めてまれではあるがないことはない。通常であれば本土に調達にでる島民に持たせそれを尾張知多の幡豆城主である千秋氏に配送依頼する。しかし、この場合、特別の配慮等は一切無いので書状に書かれてある内容を機密にしておくことは困難である。また、途中で書状そのものが失われることさえもありえる。また、このルート以外の配送方法と言えば、おんべ鯛での伊勢神宮経由があるが。こちらのルートでも機密情報の保護という点では前のルートと大差はない。おりしも街道は北朝勢が占めている。「親王が護衛のない状態で篠島に居るので迎えに来て欲しい」などと書いた密書が敵方に渡たれば直ぐここに攻め寄せてくるにちがない。仮に敵方に渡ったとしても暗号化されているなり何なりで内容を敵方に悟られないようにしなければいけない。
顕信はもしかしてと思い目西に尋ねた。
「そなたは忍家で育ったそうだが。仮に敵方に密書が盗まれたとしても敵方に内容を悟られぬような工夫でも知っているのか」
「知っている」
「どのような方法だ」
「忍家の法。主上ですら明かすことあな(だめである)」
「お主が書いた文をわしが読んでも分からぬか」
「あな(分からぬ)」
「では、忍家なら分かるのか。主上は分かるのか」
「伊賀忍家であればあや(分かる)、主上ではあな」
「伊賀忍家が密書の内容を吉野に伝えるというのか」
「あや、案文を渡さば」
謙信は半身半疑であった。だが、こやつは実は自分の腹違いの兄弟である。ましてその母親はかの中宮である。所詮だめでもともとなのだ。この目西を使うしかある
まい。
目西は幼少の頃に伊賀予野の里を離れ木津川上流の伊賀神戸で育った。物心ついたときにはすでに様々な諜報活動にその才は利用されていた。かつて伊賀の領民にとって伊賀を半ば支配する東大寺の荘司達との争いは利害どころか生死まで左右する重大問題であった。自分の土地は自分で守るのが基本。それ故、自ずと諜報活動の重要性が増したのであろう。この土地では他の地では見られぬほどに諜報つまり忍術が発達した。
千賀地家配下の神戸家は僧兵や僧侶に偽装し畿内、特に大和奈良の寺々を巡り東大寺の情報を収集していた。なかでも東大寺の比較的近くにある元興寺(がんごうじ)に身を潜め東大寺の様子を伺うことが多かった。神戸一派に連れ回されていた目西にとってこの寺は、実はお気に入りの場所であった。多くの寺は南に正門、つまり南大門をもつ。無論東大寺もしかりである。そこから北に伽藍が伸びるのが普通である。しかしこの元興寺では東門が正門。門をくぐる者が西方極楽浄土へ赴くことを意図している。寺の本堂も極楽堂と呼ばれている。目西にとって西を正面にして進めるこの寺は何よりの場所であった。(現在におていも近鉄奈良駅前に通ずる門前の通りは人呼んで「ひがしむき」である。)さらに地理的にもこの元興寺は伊賀神戸の真西に当たっている。西向きの目西が気に入るのも必然的結果であった。目西の好き嫌いとは、一般人のような情緒的な心の問題ではなく、論理的な結果として判断されるものなのである。
ところでこの元興寺には非常に大きな五重塔が立っているが(安政年間に焼失し現在はない)それとは別に高さ二尺の五重小塔(現存し国宝)なる寺宝がある。この小塔の作られた天平時代からそのきめの細かい細工のせいか、代々住職達から大切に保管されてきた。一方、この五重小塔とほぼ時を同じくして神護景雲四年(770)に高さ一尺の三重小塔が十万基も奉納された。これらは百万塔と呼ばれ天平宝字八年(764)恵美押勝の乱における死者の追福修繕のため女帝称徳天皇の発願により作成されたものであり、この元興寺の他にも南都を中心とする合計十カ寺に奉納されその総数は百万基にもなる。このおびただしい数の故にか、五重小塔とは全く対照的に代々僧侶達は百万塔をあまり丁重には扱わなく、様々な物に流用してきた。また、一基紛失しても重大な問題にはならなかったのであろう。
百万塔の塔身中空部には陀羅尼が入っているが、あるとき、その陀羅尼を抜き中に密書を入れて保管にするのには極めて都合のよいものでることに神戸達は気がついた。一般人が小塔を見れば普通は中に何かが入っているとは思わない。たとえ思い浮かべたとしても、お経ぐらいのものであろう。まさかそこに密書が入っているとは思わない。神戸達は実際に東大寺から盗聴した荘園に関する情報などを密書にしたため、百万塔に挿入し伊賀に送り届けた。いつしか伊賀神戸を始めとする伊賀忍家では百万塔をはじめ小仏塔類に機密書類を隠すことが一般化し、小塔と言えば密書、密書と言えば小塔、特に百万塔を思い浮かべるようになっていった。
そもそも百万塔の場合、塔身部である三重塔と蓋となっている相輪部が分離できる構造だとは思わない。百万塔は木製で、轆轤で作られたものであるが外部は当初、白土で覆われていた。ただ白土の大半は脱落していて木が露呈している。これらの百万塔をさんざん密書の運搬や保管に使い回すうちに忍家の誰かがより機密性を上げる工夫を考え初めた。たとえ盗まれても密書がばれる事がないように密書を入れてから塔身部と相輪部を分離できないように完全に固定してしまう。伊賀忍家であれば、蓋が固定されている百万塔内には必ず密書があることが分かっているので、蜜書を取り出すときはこの百万塔を破壊すればよい事が分かっている。しかし、いちいち破壊するのは面倒である。やがて今度は使い勝手を上げる工夫が求められた。そしていくつかの試行錯誤の末、栗の木製の相輪部が発明された。実はこれを発明したのは目西な
のだ。
目西もしばしば元興寺を出て東大寺の正倉院を目にすることがあった。目西はあの単純に見えて複雑な檜造り、単層、寄棟本瓦葺き、高床式の倉庫の造りにいたく興味を惹かれたらしい。寺院の関係者に会っては正倉院の造りついて質問攻を行い相当に煙たがられていた。それでも目西は北倉と南倉は大きな三角材を井桁に組み上げた校倉造りであることを知り、またいかなる樹種であろうと湿気により木は膨張しまた乾燥すれば収縮することなどを聞き知った。
百万塔の塔身部は檜製だが、相輪部はもともと桂か桜製である。目西は校倉造りの材と材の間の隙間が湿気で変化することを、百万塔の塔身部と相輪部の隙間にも適用して考えた。確かに百万塔全体を水につけると塔身部と相輪部は共に膨張し簡単には外れなくなった。ただ完全に外れなくなるのには水に相当長時間つけなくてはならなった。そこで目西は手近にあったいくつかの木材で相輪部と同じ直径の蓋を作って水につけては締まり具合を確かめた。そして栗材を使用したときそれは最も短時間で締まることを発見した。また緩めるために炭火に近づけ乾かすのだが、短時間で締まるものほど短時間で緩むことにも気がついた。こうして栗木の相輪部を蓋とした密書運搬の百万塔が完成した。中に密書を入れ水につけて封印する。中身を出すときは天日あるいは火にかざし塔を乾燥させる。
目西は言葉少なではあるが、顕信に密書を送るにはそれ相応の運搬専用器がいることを説明し、それを作製するのには半月かかる事を言った。また地名を、つまり篠島という文字を密書の文面そのものに書いてはいけないこと及びできれば文面全体も暗号化されているべきであることを謙信と二見に納得させた。また顕信に文面の起草をするようにも言った。そこまで言った目西は、早速密書送付の準備にとりかかりたいとて医徳院の本堂を出て行ってしまった。その後を顕信と二見は追って寺をでたが目西の姿はすでになかった。やむなく顕信は例の井に行き手酌で水を飲んだ。水で頭が冷やされたせいであろうか、顕信の焦燥は薄らいでいた。