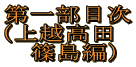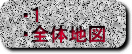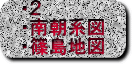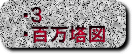北畠顕信とは裏腹に、この篠島に漂着して以降、皮肉にも宮はむしろ今までよりもはるかに元気である。無理も無からぬこと。未だ年端も行かぬ少年である。戦を眼前にした陣中にいるより、また有職故実に煩い宮中にいるより、この島で何の必要に迫られることもなくのんびりしている方がはるかに楽なのだから。この宮をこの島からお救い出すことが本当に良いことなのか。時間ばかりがむなしく過ぎていく顕信にとって、それすら疑問に思えてきつつあった。
宮を宮たらしめているのは権威でもなく宮自身でもない。権威は宮だからあるのであって、権威があるから宮となるのではない。何が宮を作っているのか。それは、血筋であって、御座所であって、家臣団であって、有職故事のごとき祭りごとのきまりが造っている。もしこのまま島に永久にいたら。いつしか宮は宮でなくなるので
ある。
帝にとってこの親王でなければならない理由は。寵愛する康子との御子だからか。確かに同母兄である恒良(つねよし)親王は建武元年(1334)に立太子されて皇太子であられる。この親王は既にお亡くなりになられている。だとすれば、義良親王が。多分それは違う。この親王は数ある親王の内の一人にしかすぎない存在。であれば、ここで顕信が努力し親王を帰還させることの意味は。いっそのこと、ここで親王を見捨てても良いし、自分自身も帰還せずこのままこの島の長にでもなり土着することも可能である。
夜、島長の館の一室に顕信は一人で篭っていた。顕信は密書の文面に関して悩んでいた。篠島の文字は文面には表さずに単に親王がおわすので使いの者をよこせとのみ文章化すれば良いのだが。ただ、まともにこれを書き記したのではあまりにも芸が無さ過ぎる。暗号化しなければならない。またその暗号は吉野において誰かがきちんと復合化し解釈できなくてはならない。
夜更けに顕信は一人もんもんとスナメリの蝋燭の下、硯を見つめ考え込んでいた。ふと緊張から覚めると鈴虫の音が聞こえた。こんな島でも秋には鈴虫が鳴くのか。時は秋である。せっかく硯に向かっているのだから秋の歌でも一首詠むか。都や吉野にいる頃はよく歌を詠んだものである。都に較べ吉野は山深いがためか、秋には鈴虫も鳴くが鹿もなく。鹿と秋か。「古今集」にある、紀貫之の歌を思い出した。
小倉山 峰たち鳴らし なく鹿の
へにけむ秋を 知るひとぞなき
顕信は、はっとした。そうだ、これだ。顕信は気がついた。この歌だ。教養や学識のある公家や高僧ならわかるが、多分無知無教養な武士どもにはわからないはずである。教養や芸能こそが貴族の最大の武器。それは、歌を用いること。歌に暗号を忍ばせる方法。この貫之の歌は冠(かむり)である。つまり五七五のそれぞれ先頭の文字をつなぐと、この歌では“おみなえし”となる。逆に沓(くつ)という技法では五七五のそれぞれ最後の文字をつなぐ。時として冠沓と言われる技法では、冠と沓の両方を使用する。
顕信は一挙に集中して、硯にむかい書き上げた。それも万葉仮名だけで書き上げた。また、冠りを悟りにくくさせるために五七の区切りを無視し強制的に九文字十二行にして書き上げた。
牟之津伎能津喩止奴
連多流能能美須乎美
須本之加良波己連阿
津女多之己止加良久
能美多流美須能之呂
計連波万津能称能以
能須伎多流之乎能美
加計止毛天津能佐比
多流千伎利能波余久
余久之乎能久佐美佐
良万之之良称止毛万
美須本之津喩阿津女
* * *
一方、目西は目西で、篠島の文字を符号化することにかなりの時間を割いていた。伊賀忍家に伝わる忍者文字を使うか。目西の数少ない持ち物のひとつである螺鈿装飾蓋の箱の中には忍者文字の五十音表が入っている。がしかし、この一言一言が単純に一対一で変換されただけのこの符号化ではいかにも単純すぎる気がした。一対一の符号化の場合、出現する記号の出現頻度が、通常文の日本語として現れる五十音の出現頻度と本質的には一致するはずである。だからその気になればすぐ復合化されてしまう。そこで、目西は単純符号化するのはやめて、透かしで篠島と入れようと考えた。暫く思考の後、目西は顕信の元に行き、顕信の書を中央から真二つに切った。そして、一枚目の先頭に、「参拾壱ヶ条」と書き記し。さらに、二枚目の末尾には「伊賀上神戸ヶ介」と書き足した。これは実際の宛て先である。そしてさらに一枚目の「ヶ条」のすぐ右横に目立たないよう薄墨で点を縦に二個書いた。目西は一枚目の上に二枚を重ねた上、スナメリの燭の灯かりで二枚を透かしてじっと見つめた。それから二枚目を引き出しおもむろに「ヶ介」部分のやや離れた右横、と言うより顕信が書いた文章の最終行にある「喩阿」と言う字のすぐ左横に、一枚目と同様に薄墨で点を縦に二個書き足した。そして再び二枚を重ねた上、スナメリの燭の灯かりで二枚を透かした。それを、顕信にも見せた。それを見た顕信は深く何度も頷いた。
* * *
翌朝から目西は狂ったようにのこぎりとノミを振るった。密書を送るための運搬専用器を作るために。つまりそれは、伊賀忍家で使用してきた百万塔を作ることを意味している。しかし、この島には栗の木がない。目西自身が発明した鍵機構を作り込むためには栗材のように水分膨張が大きい木材が必要である。そこで目西は島にある、いく種かの樹を切り出し、目の方向と大きさを揃え乾燥させた後、それらを、自身が発見した井戸から汲み出した真水を吸わせ、膨張の程度を比較した。結果、先日尾張へ調達に出向いていた島民が持ち帰った、幡豆神社の叢林のウバメガシが最も膨張した。逆に、元亨三年(1323)の第三十四回の式年遷宮の際に古くなくなった伊勢神宮の用材がこの島の八王子社と神明社の遷宮用に下賜されているが、その檜が最も膨張が少ないことが分かった。この結果から、目西は、相輪部をウバメガシで、塔身部をかつて伊勢神宮に使用されていた檜を用いて作ることとした。
目西は奈良の元興寺にあった本物の百万塔の映像的記憶や、あるいはかつて自分がそれを模倣し百万塔を作成したときの感覚的記憶を基に、できる限り本物に近い密書運搬用の百万塔を造ろうと努力した。物も言わず西を向き毎日、毎日、目西は百万塔作りに没頭した。本人の気に入るまで何度もやり直し、作り直すのでなおさら時間がかかった。その間、顕信は決して目西を督促することはしなかった。塔身部ができてからも、それとぴったりあわせるように、合計五回、蓋であるウバメガシの相輪部を作り直した。
伊勢神宮の十月の神嘗祭(かんなめさい)のために奉納する、干鯛(ひだい)の御贄(みにえ)を調整するのに二見と島長は追われていた。島の漁師兼船大工達も、伊勢神宮から下賜された太一御用の御幟を八名乗りの専用船に建て、飾り付けで忙しかった。その船大工の一人から難破した御座船の用材や装飾の一部をおんべの船に使いたいとの申し出が神職二見を通して顕信にあった。にべなく断ることも可能である。だがふと顕信は考えた。船大工達の申すとおり御座船を彼らの手で修復することは不可能である。だったら御座船を放置しておく意味は何もない。何かに利用すべきである。ここで船大工達の申し出を許可すれば、親王の心の広さを示すことができるであろう。また、親王の伊勢神宮に対する信仰心から御座船の用材を快く提供したのだと言うこともできる。と言うわけで顕信はこの申し出を快諾することとした。
明後日、天気は晴れていた。親王がおんべ鯛祭をご拝見しておられる事実と、先日の顕信の取り計らいのせいか、島民の多くは普段のおんべ鯛祭より遥かに興奮していた。神職二見貞友自身が取り仕切った儀式の後、二見は伊勢に向けて出航していった。二見は密書の入った百万塔を抱きしめていた。Copyright(c) 2019. Gigagulin (偽我愚林)