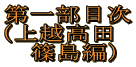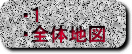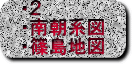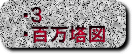島長の篠島太夫が島を出るというので北畠顕信は非常に懸念した。情報が漏れては大変である。何度も島長にこの島に親王が居ることを喋ってはならないと念を押した。二見貞友を同行させるようにも言ったが断られた。どうしても不安な顕信は、神職二見を伴わせ神明社に行き島長に神前で誓いを立てさせた。
年に二度、元日から十日目の日と、百八十日目の日に、篠島の長(おさ)と佐久島(さくしま)の長と日間賀島(ひまかじま)の長とで会合をもつのだと言う。場所は輪番制で、今回は日間賀島で開催される。その会合に出席するために篠島太夫は島を出立するのである。
篠島が最も伊勢湾側(伊勢湾口)で南西に位置し、そこから、北に向かって2.7kmの三河湾口に日間賀島、さらにそこから北東に向かって3.5kmの三河湾内に佐久島がある。もともと篠島と併せこれら三つの島は古代には、いずれも参河国播豆郡(三河国幡豆郡)に属していた。奈良時代には各島で月ごとに佐米楚割(さめのそわり)を調として朝廷へ貢上していた。尚それぞれの島の古表記は篠島が小竹嶋、日間賀島が比莫嶋、佐久島が析嶋である。いずれの島の民も海部(あまべ)と称される漁民であった。
篠島は律令時代以前から伊勢神宮との関係が他島よりも強かった。源平期に宝賀秋季が篠島に砦を築き、篠島を中心に伊勢湾と三河湾を支配した。その後、鎌倉期には篠島は志摩国答志郡篠島となり、そしてこの頃は伊勢との強い結びつきから伊勢国度会郡篠島となっていた。一方、日間賀島は知多半島に最も近く、半島の岬から直線距離ではたかだか2.5キロメートルしか離れていない。そのため尾張との結びつきが自然と強く、伊勢、三河とは縁が薄くなっていた。また、佐久島となると知多半島からは逆に最も遠くなり三河が最も近くなる。三河の吉良(現在の吉良町ではなく一色町)まで6.4キロメートルである。故に佐久島は律令以来三河国幡豆郡の支配下で伊勢や尾張との縁は薄かった。ちなみにそれは現在でもそうで、佐久島だけ三河の一色町に属し、篠島と日間賀島は尾張の南知多町に属する。従って佐久島は尾張知多側との定期船の往来もなく現在では全く異なった文化圏となっている。
御互い約3キロメートルずつを隔てているに過ぎないのだが、篠島は伊勢、日間賀島は尾張、佐久島は三河と繋がっていた。顕信が特に懸念したのは佐久島と三河の繋がりである。鎌倉幕府末期まで三河は足利の所領であった土地である。そして今、足利家支族の吉良貞義が同地を支配している。万が一にも義良親王と鎮守府将軍が篠島で過ごしていると分かれば、明日にでも水軍を仕立てて攻め入ることの可能な距離である。顕信にとって新年から頭の痛い問題であった。ただ、今にして思えば流れ着いた場所が佐久島ではなく篠島であったことは不幸中の幸いと言えた。
漕ぎ手二人と島長の甥との合計四人で篠島を立った。隣の日間賀島まで海流や風、波にもよるが、半時(一時間)とかからずにいく事ができる。真冬の海だが比較的穏やかで、直ぐに日間賀島の南東側の湊に着いた。ほぼ時を同じくして佐久島からも長一行が到着した。長の名は海部借持(あまべかりもち)と言う。篠島太夫よりもやや若く、中肉中背だが色黒で鬚も長く実際以上に大柄に見える。取り巻きも七人おり太夫達を圧倒した。その取り巻きの中には明らかに吉良氏の紋付(二つ引両)を着用しているものもいた。
程無くして湊から比較的近くにある大光院(現在も大光院)の庫裏に全員が集合し年二回行われる三島の長会議が始まった。寺の庫裏の部屋は畳でも板間でもなく竹のすのこになっている。夏は涼しくてよいのだが新年の時期には寒い。この部屋は約三十畳あり、実はこれ以外、多勢が会議できる場がなかった。日間賀島からは長の比莫太夫他五人が参加している。篠島からの四人、佐久島からの八人と合わせて総勢
十七人。
司会役は会議の場所となっている島の長の役。従って今回は比莫が司会。比莫太夫は年も風体も篠島太夫と海部借持の中間といったところである。彼の後ろ盾は師崎城の千秋氏と考えられている。この男の音頭での年始の挨拶が終了し、新年の祝いの御神酒を飲み干した後、本題に入った。本題と言っても事前に決められた議事が有る訳でもなく情報交換が中心である。佐久島の長は、三河から東海道の、時として鎌倉方や北朝系の情報、日間賀島の長は、尾張とまれに東山道の情報、篠島の長は、伊勢から西国あるいは朝廷関係の情報を話す。それが基本であった。その他、自分の島での話題を紹介しあう。また、前回の会議からの宿題事項の結果を報告することもあった。そんな中で次回の会議までに協力して何かやることでもあればそれを議論し決定していく。
この日も、特に順序があるわけでもなく、五月雨式に情報交換が始まった。いつも会議をリードするのは司会役ではなく海部借持であった。
「吉良殿によれば」借持の切り出しは大概この言葉から始まる。吉良と自分は対等に普段から話し合っているかのようにしゃべるのである。
「篠島殿も比莫殿も、昨年秋ごろ、伊勢大湊から南朝側の大船団が出航したことは知っておるだら。遠州沖で大風に遭いその船団は散り散りになったことも知っておるだら。幾つかは沈没し、また幾つかは海岸に打ち寄せられ、幾人かは助かったらしい。それでじゃ、吉良殿によれば、近衛中将である北畠顕信と総大将である義良親王を乗せた肝心の御座船の行方が未だに知れないと言う。南朝方にはさぞ大打撃だら」
借持が「北畠顕信と義良親王」と口にした瞬間、篠島太夫は口から心臓が飛び出すほどに狼狽した。寒気が一層強くなるのを感じた。それを見た比莫が言った。
「篠島殿、どうしたのじゃ。大丈夫きゃ」
「あ、いや、大丈夫じゃ」
「肝心のその御座船は見つかっていないらしいのだが、つい先日、吉良殿の下に一品中務卿宗良親王の消息が入ったのじゃ。というのも吉良貞義殿と同盟関係にある遠江の今川範国殿からの話ではの、どうやら親王の隊は、天竜灘は白羽に漂着したらしいのじゃ。そこで、今川殿も、この親王を討ち捕らば、さぞ足利殿からの恩賞があるとて、一線交えたと言うのじゃ」
比莫は大きく頷きながら借持の話を聞いていた。また、借持の話が顕信と義良親王からそれた事に篠島太夫は安堵を感じ、なんとか動揺を隠しつつ話を聞いた。
「ところがじゃ、吉良殿に今川殿からの援軍の要請も全くなく、多分、今川殿も一人で功をあせったのだらーて。卑怯にも背後から南朝方の井伊高顕や天野景隆らが今川殿の背後を突いたで、今川軍も総崩れじゃ」
「それで、親王はどうなったのきゃ」
比莫が結論を知りたがった。
「比莫殿も篠島殿も、南朝方だら」
「わしらは、北朝とか南朝とか関係ないだもな。島にはどちらがどちらでも関係ないだもな。まして、下々の漁民らーは南朝も北朝も、そんな言葉すら知らんだもな。海部殿は北朝方だからの。今川殿が負けたら困るじゃろうて」
「わしとて、ことさら北朝方というわけでもないがの。足利高氏殿や吉良貞義殿も三河の支配者じゃからな。島としてはさんざんにお世話になっとるだら。」
「あまり、どちらか一方に荷担せんほうがええだもな」
「そりゃまあそうじゃが。どちらかと言えば佐久は三河だら、足利高氏殿や吉良貞義殿にお世話になっとる分は荷担せーへんといたしかたあるまいだら。たとえ、今川殿が南朝方の親王に一回きり敗戦したからとて、今の趨勢では北朝方のほうがまだましだらーあ」
篠島太夫は比莫と借持の話を聞いていていよいよ寒くなくってきた。もしこのまま島に義良親王が居座りつづけそれが世間に知られれば。吉良や足利に篠島は潰されてしまう。そして、自分達がそれに荷担していたとわかれば、自分達も処刑されはしまいか。ならば、いっそうのこと、ここで借持を介して吉良に密通してしまえば良いのでは。
篠島太夫は今更、二見が北畠顕信らに協力的であることを恨んだ。二見にそそのかされさえしなければ。色々な考えがめぐり寒いにも関わらず汗がでるのを感じた。
「それから親王はどうなったんきゃ」
再度、比莫が借持に尋ねた。
「それから、親王達は井伊道政に丁重に迎えられ、井伊(現、静岡県浜松市引佐町井伊谷(いいのや))の三岳城に入城したとのことじゃ」
「ほう。それから」
「いや、話はここまでじゃ」
「ところで、篠島殿。大丈夫か。さきほどから黙り込んでおるが。顔色が悪いが、調子が悪いのでは」
比莫が尋ねた。
「あ、いや、大丈夫じゃ」
もともと、篠島太夫は口上手ではなく、話が苦手でもあり、自分の思考を相手に満足に伝える能力に欠けていた。
「無理はせんほうがいいだもな」
もともと、比莫は、海部借持の性格も、篠島太夫の性格もある程度は知っている。比莫は借持の強烈な話ぶりで篠島が圧倒されていて喋ることができないのであろうと察した。そこで比莫は司会役として話題を変えてみた。
「ところで、篠島殿のところに居付いた、変わり者、名を何と言ったかの。その後、その変わり者はどうしておるかの」
「あ、いや。名は目西じゃ。あまり変わったことはないで」
「そうか」
「あ、そう言えばな、先日、奴が井戸を見つけたのじゃ。どういわけだかわからないがの、その井の水、島では珍しく辛くなくてな」
「それは珍しいの。うちらの島じゃ井戸は塩辛くてたまらーんわ」
「わしは、時々、奴は変わり者と言うより、正直、妖術使いかはたまた魔に憑かれた餓鬼か何かではと、思うことがあるでな」
「それは面白い。その餓鬼に会ってみたいの。また塩辛くない井の水も是非とも飲んでみたいがー」
話を聞いていた、借持が言った。
「そうだもな。いっそのこと今から皆で篠島にいくというのは」
聞いていた篠島太夫はおおいにあせった。断らなければ大変なことになる。本当に海部や比莫が島に来たら大変である。義良親王の御座所がばれる。
「あ、いやいや、めっそうもない。長達がくるにはそれなりの、準備というか、とんでもござらぬ」
「準備などいらぬではないか」
「あ、いやいや、失礼になるとわしとしても困るでな」
篠島太夫は、井戸のことに振れたのは拙かったと思い、馬鹿なことを言ってしまったと後悔した。太夫は守りに必死で、逆に自ら北畠と義良親王を裏切り安泰を得る作戦など頭から吹っ飛んでしまっていた。そして、かたくなに借持や比莫の申し出を断りつづけた。そして愚直な拒絶がなんとか功を奏してか、一件落着した。が、しかし、比莫も借持も近々、篠島を訪問するということになってしまった。
* * *
北畠顕信は一連の話を島長から聞き深く溜息をついた。もし日間賀島や佐久島から人が来たらどうするか。悩ましくうっとおしい問題を抱えこんだものだと思った。結局、島長に有力島民を招集させ会合を開き、港に他島から人が来た場合は至急顕信に連絡することとした。また、連絡を受けたら島民に手伝わせ御座所を急ぎたたみ義良親王とともに武士団は神明社の神殿に隠れるということにした。また改めて島民に親王がこの島にいることを島外で言及することご法度であることを確認させた。
が、実は顕信にとっては、他島のものが来てしまうことよりも一品中務卿宗良親王の件の方がはるかに気がかりな問題であった。気がかりな点は三つあった。内二つはある意味で相矛盾する観点での心配事であった。
最も気がかりなのは、南朝側の軍事的観点からのものであった。今回の東国遠征で何隻沈没したのか。戦わずして負けたも同然である。もし軍を建て直しする場合どうするのか。反足利勢力の結集が必須であろう。その場合信州が鍵である。なぜならば、北条時行の中先代の乱も信州更埴から挙兵したように、未だに信州には北条残党勢力が多数存在し反足利の拠点となっているからである。従って信州との接触は反足利勢力結集の最重要要素であると考えられる。しかし、吉野から信州へのアクセスにおいて、東山道あるいは東海道経由では途中に北朝勢力が多く直接的には到達し得ない。しかし、吉野から伊勢に出て海路、遠江天竜にまで出られれば、陸路秋葉街道を北上し北朝方に遭遇することなく信濃にアクセスできる。今、その入り口とも言える井伊谷の三岳城に宗良親王が入城されたということは信濃へのパスが開かれたことを意味する。そのこと自体は極めて歓迎すべきことではあるが、顕信は同時に心配もしていた。宗良親王で果たして大丈夫なのか。顕信はあまりこの親王のことを知らなかった。知らないことは顕信にとってすべて心配の種となる。ただ、顕信の知る限りでは宗良親王はしたたかな人物である。大塔宮がかつてそうであったように、この親王もはじめは尊澄(そんちょう)法親王と呼ばれる天台座主であったが、戦のために還俗したのである。そして今日まで戦い続けている。生き残っている親王なかでも最年長であるのだ。
次いで気がかりな点は、正に宗良親王が最年長であることである。この親王が帝になったとしたら。義良親王はどうなるのであろう。それはそれで大きな問題ではないかもしれないが、やはり気にはなる。それ以上に逆に義良親王が帝になった時、この親王の処遇をどうしていくのかこれこそ問題となるかもしれない。
そしてもう一点の気がかりは、同じ南朝の武将としての気遣いという観点からであった。同じ船団で同じ東国遠征に出立しそして難破した。味方の無事を案ずるのは当然のことである。ただ、顕信自身気がついてはいるのだが、この親王がいなければ事はもっと簡単なのにと。しかし、南朝側の重臣として、味方が減るのは嬉しいわけがない。様々な意味において、この親王の存在は複雑な気持ちを生じさせた。
Copyright(c) 2019. Gigagulin (偽我愚林)