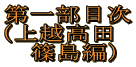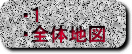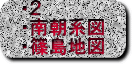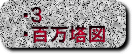目西の出自を知っているものは篠島には皆無である。島長の篠島太夫も、神職の二見貞友も。実は二年前の夏、熱田大宮司家である千秋氏の使いと名乗る猿楽師が彼を島に連れてきたのだが、その際の書状に「性質奇怪なれどもさる高貴な御方のご落胤故」と記されていたこと以外何も知らされていない。目西本人が持ち込んだ蓋に螺鈿のある箱がいかにも貴族の持ち物のようであること以外、彼が高貴の出であることを証明するものはなにもないのである。その螺鈿蓋の箱の大きさは長さ一尺程、厚み幅ともに三寸の直方体である。本体といってもさほど蓋の部分と大きさは変わらないが、この本体は蓋と異なり何の装飾もない。もちろん中に何が入っているのかは目西以外、誰も知らない。
島長の舘で目西の唯一とも言えるその持ち物を偶然目にしたとき、顕信は衝撃を覚え即座に島長に誰の持ち物かと問うた。その答え、つまり目西のものであることを聞いたとき彼の衝撃は怒りになった。しかし彼はその動揺を人に悟られまいと努めた。顕信自身ほぼ同じ箱を所持しているのだ。かつて父、北畠親房から箱を授かった。蓋は天、体は地。蓋は帝、体は臣。蓋は公家、体は武家。つまるところ蓋と本体で、文武両道を意味し、かつまたそれは、北畠家そのものを象徴的に意味している。そもそも北畠家は大臣(おおおみ)の家格たる中院(なかのいん)家の一族で、村上天皇を祖とする「村上源氏」の一門である。つまり帝に仕える臣であり、親房自身大納言であり、また武家の棟梁たる存在でもある。兄顕家にしろ、自身顕信にしろ、公家とはいえ生涯の大半を戦で明け暮れ過ごしてきている。雅な宮廷生活とは如何なるものか顕信には分からないほどであった。
この度の義良親王を奉じての東国派遣に際し、正確に言うと、それに先立つ二ヶ月前の閏七月二六日、帝からの勅命で従三位近衛中将陸奥介鎮守府将軍を顕信が賜った際のことである。父である親房から聞いてはならぬ秘密を打ち明けられた。二十歳そこそこの顕信の道徳感にとっては許しがたい父の裏切りとも言える内容の話ではあった。花将軍と皆に謳われ将来を嘱望されていた兄の顕家がつい先だって高師直との石津合戦後、阿部野で討ち死にしてしまったことが父を焦らせていたのかもしれない。父はもとより帝もその才気に期待をかけていた嫡男たる兄がである。顕家を失った父としては悲しみ以上に一刻も早く顕信に北畠家の家督相続者たる自覚を持たせるために、あるいはこのとんでもない秘密を打ち明けたのかもしれない。
文保二年(1318)親房、二十五歳。正二位。時の帝の第二皇子である世良親王の養育係としての日々を送る中、長男顕家が誕生した。その翌年の元応元年(1319)八月、太政大臣西園寺実兼(さねかぬ)公の娘禧子(きし)が中宮となった。もともと現帝がまだ尊治親王時代のことである。立太子した直後の正和二年(1313)の秋、西園寺実兼公の屋敷からこともあろうに齢十そこそこの禧子を連れ出してしまうという一種の恋愛事件を起こしたことがあった。それから六年の歳月を経て、親王ではなく帝としてこの愛してやまぬ禧子を中宮として向かえたわけだが。実はその間の正和四年(1315)に禧子は皇女を設けている。その子は名を懽子内親王(よしこないしんのう)と言い後の北朝第一代光厳天皇の中宮となる。現代の感覚では信じられない年齢での出産である。
今、禧子は御年16歳。中国の名高い美女、モウショウ、西施(せいし)も己を恥じて顔を伏せ、ゴウキ、青琴(せいきん)も鏡を見る気をなくすほどと歌われた美女に成長していた。さてこそ、帝の寵愛を一身に受ける筈であった。ところが、禧子とともに、阿野中将公廉(きんかど)公の娘で康子(れんし)と申す上臈が入待した。<太平記現代語訳>
実の所、禧子よりも歳は三つ上。美貌であることには間違いないが、中宮禧子に較べて果たしてどうか。親房もこの年、中納言にまで昇進し禧子や康子を見かけることがままあったが、美しさは禧子が優れると思った。その一方で歳の差分であろう、正直、康子のほうが性的な魅力が高いと感ずることもあった。案の定、当の帝は何をどう感じたか定かではないが、中宮を相手に選ぶことなく、康子を毎夜の伽として選ばれた。宮中のうわさでは康子は所謂才色兼備で、言葉巧みに帝を誑かすと。康子は年下の禧子には負けたくないとの思いでもあったのかもしれない。しばらくして帝は康子を准后とする勅命を出した。
一方の禧子は弘徽殿(こきでん)の中のお人形様である。帝ただ一人を信じて入待したわけだが、生涯、帝の御側に侍されることがなかったのである。春の暮れるが遅くを嘆き、あるいは秋の夜長を恨み、物思いに沈まれるお暮らし。見た目の煌びやかさとは裏腹に口数も少なく、変化のない毎日を送られていた。
<太平記現代語訳>
ちょうどその頃、元応二年(1320)に親房の次男として顕信が生まれた。また、この年に親房は淳和院の別当に補せられた。この職は代々村上源氏の代表者が当たってきた故、親房が源氏の棟梁であることを印象付けた。この頃からであろうか、親房は禧子を特別不憫に思うのと同時に彼女の愁美に惹かれ始めた。そして親房は毎日、禧子の側に一歩づつ近づく努力を始めた。しかし相手は中宮である。そう簡単には行くまいと思っていたが、確実に一歩、一歩近づくとそれなりの成果があった。そしてそれは元享元年(1321年)についに実を結んだのである。その結果として禧子は懐妊したのだが、宮中の誰の目から見ても帝の御子でないことは明白。ただ主上(帝)の性に対する大らかなご性格と、鎌倉幕府の手前突き入る隙間を与えたくない朝廷側の微妙な力学が作用して、悩める親房とは無関係に、いつのまにか中宮禧子は帝の御子を身ごもったこととされた。元享二年(1322年)春には、法勝寺の円観上人、山科小野の文観僧正、以上二人が勅命を受け、宮中に祭壇を設け中宮御安産の御祈祷が盛大になされたのである。この御祈祷には実は裏があり、関東北条方を呪い滅ぼすため中宮の懐妊にかこつけて秘法を実施したとのことである。
<太平記現代語訳>
つまり中宮懐妊は秘法実施の丁度よい口実とされたわけでわる。
元享二年(1322年)秋には親房と禧子の間に男子が生まれた。しかし、明確に帝の御子ではなく生まれた男子は密かに宮中から消され、表向き中宮は流産したこととなった。
さて、親房は愛しい禧子との間の子をそう容易く抹殺する気には成れなかった。そこで親房は密かに伊賀の国予野の忍宗家である千賀地(服部)保親にその赤子と北畠家の証として螺鈿蓋の木箱を託した。実はかねてより親房と千賀地保親には関係があったという。伊賀の土地の大半が実は大和東大寺の荘園であり、土着している千賀地一門と東大寺から委任された荘司達との間で、四至傍示(ししぼうじ)の位置をめぐる争いが絶えなかったらしい。土着勢力である彼らは鎌倉幕府から荘園管理に遣わされた地頭等と異なり、荘園領主勢力と下地中分(したじちゅうぶん:紛争解決に幕府が裁定)等の公的措置での紛争解決は取りづらかった。そこで、彼らが頼りにしたのが中央の有力貴族による仲介であった。過去に何度か親房は彼らと東大寺間を仲介し彼らの窮地を救ったことがあったのだ。それは所領安堵の綸旨を発給することである。その礼に千賀地一門はその持てる諜報能力の一部を親房に提供してきたのだ。ちなみに後年のこととはなるが、建武の新政のおり、親房のために活動していた千賀地保親のこの諜報部隊の一部は楠木正成公に割譲され透波(すっぱ)四十八人衆と呼ばれることとなる。
かくして、目西は忍家の中で育つこととなった。ただ目西が尋常の子でないことは成長するとともに明らかになった。言葉を覚えるのが遅い。覚えた後も言葉数が少ない。不思議なことにいつも正確に西の方位を当てることができる。さらに一度覚えたことは二度と忘れない記憶力、特に物を一度見ただけで細部まで記憶に留めることができる能力まである。ただ、他人が身体を触れると物凄い剣幕で癇癪を起こす癖があった。そして成長するに従い癇癪を起こしたときの暴力に周りものが手を焼くようになった。宗家にこのような異質異能な子がいるというのは、いかにも予野の集落内での聞こえが悪い。親房と中宮のご落胤と言へども千賀地忍宗家内に止め置くには迷惑だったのであろう。ただ一方で保親はこの目西の特異能力は忍家にとってはある意味で調法なものであるとも考えていたらしい。そこで予野の集落からほどなくいった所を流れる木津川の一里ほど上流に庵を作りそこで保親配下の忍家である神戸(かんべ)らに目西を養育しかつ忍者として鍛えるように指導した。その後、目西は千賀地忍宗家配下の神戸などと、僧侶に偽装したりあるいは猿楽士や香具師とともに畿内の寺社などを中心に諸国を点々としたという。