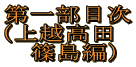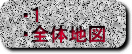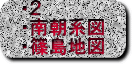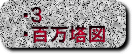今般の東国遠征の出港地は伊勢の大湊であった。今回と限らず南朝方の大軍が出港するのはほぼこの大湊に固定されてきている。吉野から直接高見峠を越えるか、あるいは明日香経由で大和宇陀を抜ければすぐに伊勢に至れることも理由であるが、外宮禰宜の度会が北畠と近しい関係であることも大きく影響している。しかし、なにより大湊の造船と廻船を掌握している問丸で光明寺の僧でもある恵観が南朝に協力的であったからというのが大きな理由である。この恵観と言う僧、うわさでは結城上野介宗広の庶子であるらしい。上野介宗広は北畠顕信らとともに別船で今回の東国遠征に出帆している南朝方の武将の一人。宗広はかつて大塔宮から倒幕の綸旨を受けるまでは鎌倉殿(北條氏)の忠実なる家臣であったそうだが。
南朝が水路で遠征する場合、北畠家がまずこの結城宗広に対し交渉する。そして宗広が仮に恵観の父だとして、問丸である恵観に行軍の兵站一切を委託する。すると恵観は軍団輸送船や漕手、果ては志摩、熊野の水軍まで手配した上、さらに軍団の兵糧調達にまであたる。この物資の調達は伊勢神宮の問丸という職業を上手く利用して行われたはずである。つまり、伊勢大湊の問丸は全国に点在する伊勢神宮の御厨(みくりや:神宮領の荘園のこと)からの産物、供物等の集積、保管、運搬等の管理一切を仕切っているのであるから、当然問丸が自己都合用にこれらを回す事は想像に難くない。そして、そこから多大なる利益が得られるのである。恵観にとって兵站一切を受託することは有益な話であるはずだ。
ところで、何故大湊が御厨の集積地に発展したのであろうか。伊勢の大湊は、大河川(だいかせん)である宮川と中河川である五十鈴川と小河川である勢田川が交わった河口に位置している。古代から天然自然の舟溜まりであり、海からは海産物が、宮川からは上流山地の良質な木材が集まり、五十鈴川を遡れば皇大神宮(内宮)が、勢田川を遡れば豊受大神宮(外宮)がある。この物流上の位置関係から当然の結果として、大湊が神宮御厨からの物資集積地となったのであろう。そしてそれらを取り扱う問丸業が発達したわけだ。
ところで、結城上野介宗広は遠州灘で難破し、そのまま彼の船は伊勢国そのものまで吹き戻されてしまった。伊勢国といっても義良親王や顕信らの船とは異なり篠島にたどり着いたわけではなく、出港地である大湊のすぐ傍に着いた。このときすでに宗弘の齢は七十。度重なる南朝側の敗戦と今回の難破である。精神も肉体も限界に達してしまったのであろう。大湊に出戻ったのだがそこでにわかに発病し、延元三年十一月二十一日(1339年1月1日:ユリウス暦)に他界してしまった。そしてそのまま恵観のいる光明寺にて埋葬された。(伊勢市岩渕の光明寺に結城宗広の墳墓現存/津市の結城神社にも祭られているが)
千賀地保親が百万塔に入れた密書を吉野にもたらした時には、既に結城宗広の死は南朝中枢部にまで伝わっていた。また中枢で最も頼りになる北畠家のものが一人もいない時期でもあった。北畠顕家は昨年戦死、顕信と親房は東国に遠征中に遭難。顕能は伊勢の国司として現地入りしてしまっている。
今、件の百万塔密書により義良親王と顕信が無事に篠島にいることが分かり、最近毎日毎日塞ぎ込んでいた帝にとって、久しぶりもたらされる明るい話題ではあった。がしかし、朝廷中枢部は非常な安堵を覚えるとともに、ただ逆にひとつの問題が浮かび上がってきた。それは、誰を義良親王の救出に向かわせるのか、また救出のための御座船の手配を如何にするのか。海路の時の手配は北畠一族に常に任せてきたが、今、彼らは誰一人として吉野にはいない。そこで北畠を介さずに直接、結城宗広に海路手配を委託ということも考えるのだが、当の宗広が先般他界してしまっている。吉野朝廷内部には実際の船の手配がどのように行われていたのか凡そ知る者もおらず途方にくれてしまった。しかし、非常に幸いと言うべきか。北畠軍団の東国遠征に忍家として協力してきた千賀地党の棟梁がここにいるのである。千賀地は南朝の廷臣達に実際の兵站任務は光明寺の恵観が執行していることを説いた。そして、恵観を説得すれば、自ずと救出作戦はなされるであろうことも説いた。
光明寺の恵観を説いて救出の任に当たる人物。吉野朝は人選に苦慮したが、結局、僧を説得にするには僧あるいは僧経験者が良かろうということになった。そしてこの救出作戦の司令長官に、つまり勅使に選んだ人物は、日野大僧正頼意(よりおき)となった。
* * *
篠島には雪が積もることなどほとんどないが、極まれに薄く雪化粧することがある。そんな薄化粧の雪は瞬く間に溶けてしまう。とは言うものの目西の見つけた井戸の周囲は篠島一高い丘の北面の谷筋に位置するため積雪から数日間は雪が残る。そんな雪の残った井戸の水はそれでも地表の雪解け水よりはるかに温かい。手を着けていても痛くならない。そう顕信は思った。そして有り難さ故にか、実に美味い水であると感じた。
いつになったらこの島に迎えが来てくれるのであろうか。密書は無事に吉野に着いたのであろうか。密書は届いたものの暗号解読に手間取っているのか。様々な思いで焦燥に駆られる。さらにまた、日間賀島や佐久島から島長や漁師達がこの井戸をいつ見に来てもおかしくない。そろそろ限界か。これ以上待っても勅使がこないのであれば行動を起こさなければならない。脱出のための。
寒さの中、顕信は井戸の側の医徳院の本堂に入り、ひたすら勅使が来ることを念じていた。そんなおり、島長と二見貞友が血相を変えて走ってきた。顕信は海部や比莫が、とうとう島に来たのだと察した。薄暗い本堂の中で二人の激しい息が白い煙のように見えた。さらに二人とも背中からも湯気を出していた。ただ事ではない。よほど全速力で走ってきたのであろう。顕信を見つけても直ぐには声が出てこなかった。
「ごご、ごっ御座舟が」
島長がやっとそう言った。顕信は海部や比莫が御座船の残骸を見つけたのだと瞬間的に考えを巡らせた。しばらく俯(うつむ)いて呼吸を整えていた神官の二見が口を開いた。
「顕信殿、御座舟らしき船が島に近づいてきます」
何かの聞き違いであろうか。顕信は疑った。
「方角は、距離は」
「伊勢が浜から見て西、伊勢側からの接近です。距離は一里。今、目西が見に行っています。やつは目が良いので」
顕信は考えた。敵方の囮か。少し落ち着きを取り戻した島長が言った。
「親王様のお迎えの船だも」
「そうであれば良いが、もし違っていたら、直ぐに親王を御座所から避難させなくてはなるまい」
顕信は目西からもたらされる情報を待とうと思った。島長は元より神官よりも目西の情報をむしろ顕信は信頼していたからである。
「目西はここまで来るの」
「何か分かれば直ぐに報告するように伝えてあるだもな」
まもなくすると、目西が歩いて医徳院に来た。
「何で走ってこんのか」
島長が叱咤した。が顕信は目西が走らない理由を悟った。敵ではないからだと。
「敵か」
「あな」
「お見方か」
「あや」
「間違いないか」
「あや」
顕信は悩んだ。多分、目西の眼力である。ほぼ見方であることは確かであろう。しかし、もし万が一でも敵であったら。当然、ここはまず敵であることを考え親王を神明社の隠れ家にお連れすべきであろう。しかし、それをすると目西を信頼していないということになる。目西は癇癪を起こすであろうし、それより何より目西との見えない心の繋がりを失うことを顕信は危惧した。しばし間を置いた後、顕信は言った。
「わかった。お見方をお迎えに行こう」
顕信は目西を選んだ。
「えつ、わしの言葉は疑っただのに、目西の言葉は信頼しなさるだもか」
顕信は島長を半ば睨みつけ頷いた。二見は半ばあきれつつも顕信の返答を予測しており、すでに医徳院から出ようとしていた。
御座所に行くと、親王は、世話係をしている親王よりひとつ二つ年上の女人と戯れていた。元来であればこのような女子と触れることなどありえない。このようなはした女に恋心でも抱いては大変なこととなる。へたをすると島から出立することを嫌がるかもしれない。もともと顕信自身が親王の気晴らしにでもなるかと思い歳の近い島の娘を世話係にあてたのだが。
顕信は親王に、勅使がまもなくお迎えに上がることを伝えた。案の定、親王は戯れをやめ不機嫌な顔になった。
「元来、これは誠にお喜ばしいことでございます。しかし正直に申し上げますると、不便でまずしいものの、この島での宮様の平和なお暮らしぶりを見るにつけ、再び戦場(いくさば)にお連れすることが良いことなのかは私にも分かりません。それでもやはり、人には身分に応じた役割がございまする。宮様のお役割は帝をお助けし天下の身分、秩序を正すことでございます。この島での宮様のご経験は必ずやお役に立ちまする」
親王の表情は優れなかった。
「今回の難破と島での生活で宮様は格段にたくましく成長なされました。宮様が立太子され、末に帝になられることを、顕信は切に願っておりまする」
聞き分けが悪いわけではないが親王自身何か思うところがあるのであろう。すぐには頷かなかった。
「朝敵を倒し再び太平の世を実現なさる方こそ真の帝王でございまする。帝になった暁に再びこの島に御行なされば」
顕信がここまで言ったとき親王は首を立てに振った。
顕信、二見、島長と目西は浜で斥候の小船が着くのを見つめていた。小舟にはこぎ手が一人ともう一人が着座で乗船していた。着座している者は、位牌でも掲げているように見えた。その小舟が近づくにつれ位牌は件の百万塔であることが分かった。それを手にしているのは質素だが隙のないみなりをした初老のものである。体つきはいたって屈強そうである。浜に着く直前にその者が顕信をみつめて大音声で言った。「鎮守府将軍北畠顕信公とお見受けいたした」
「いかにも」
斥候はついに上陸した。
「拙者は伊賀党棟梁千賀地保親でございます。お久しゅうございます」
顕信は千賀地の名こそ知れ、また、幼少の頃間違いなくあっている事を知識として持っているものの、記憶にはなかった。
「日野大僧正頼意殿、帝からの勅命を賜い、陸奥太守義良親王のお迎えに参上仕り候。拙者はこの密書を受け取りし者として、また大僧正殿の斥候役として先に上陸、内偵せし者であります。従って、まずお尋ね申すが、陸奥太守義良親王は恙無くお過ごしあそばしか」
「鎮守府将軍北畠顕信がお答え申す。陸奥宮公はすこぶる元気でございまする」
「いっさい承知仕り候」
千賀地は左手で百万塔を抱え右手を大きく振り沖に停泊している御座船に合図を
送った。
千賀地を残したまま小船が引き返すと同時に御座船が動きはじめた。
千賀地は、百万塔を恭しく目西に差出、深々と頭を下げた。
「顕実(あきざね)殿にご返却申し上げます。ご成長なさいましたな」
この千賀地の目西に対する態度に一同、驚嘆した。目西は片手で百万塔を受け取ったものの礼ひとつ言わなかった。島長は目西がさる高貴なお方の御落胤と聞いてはいたが、朝廷からの使者が目西にここまで礼を払うとは想像だにしていなかったのである。また、皆、目西の本名が顕実ということをこのとき初めて知ったのである。顕信も驚きを隠せなかった。顕(あき)は親房の男子に付けられる。考えてみれば目西の母は自分の母よりはるかに高貴なのである。正直、顕信は複雑な心境であった。
しばし言葉を互いに交わしている間にも御座船は浜に近づき、これ以上接近できないところまできて動きを止めた。すぐに御座船から一人が助けを借りつつ小舟に乗り移った。袈裟をまとっている。多分、大僧正であろう。しばらくしてもう一艘小舟がだされ、それにもこぎ手の他、袈裟をまとった僧が乗船した。
「先に見えるのは勅使、日野大僧正頼意殿。後に見えるのは伊勢国光明寺の僧恵観殿でございます」
千賀地が説明をした。この間に、島長と二見は親王の元に伝令に出ていった。
* * *
日野大僧正頼意は典型的な朝廷人であり武人とはほど遠かった。動きは鈍重で、いかにも腹黒そうに見えてしまう。真実は不明であるが。大僧正が気にしているのは親王自身のことではなく、一連の任務の無事な遂行と、それを如何に美辞麗句で並び立て報告するかということである。
この大僧正、親王や顕信らと当たり障りのない挨拶を交わした後、御座舟の準備をするとかで島から親王よりも先に出ていってしまった。実際に御座舟に親王が乗船したのは翌朝のことで、千賀地、恵観、北畠顕信及び顕実こと目西とであった。
目西が島を離れることになったのは、顕信の強い希望と、千賀地が再び目西を伊賀の里に戻そうと思ったからである。
かくて、陸奥太守義良親王は自分の意思とは全く無関係に篠島を去ることになった。そして日野大僧正頼意の詠んだ歌は、
神風や 御船寄すらん 沖つ波
のみをかけし 伊勢の浜辺に
Copyright(c) 2019. Gigagulin (偽我愚林)